�ꊇ�̔��ł��B �y�ꊇ�̔��̏ڍ׃y�[�W�i�ށz |
||
�@�@�u���y���H���_���v�����S�ł������_�I�����E���y�_���́u���y�w���v�����A�����ɍڂ��Ă���܂��B �@�@�@Johannes de Grocheio (Grocheo)�@���n���l�X�E�f�E�O���P�C�I�@1255-1320 �@  �@�����n���l�X�E�f�E�O���P�C�I �F��B�v ���V���� ����I�q�ďC �������l�T���X���y�j������� �@�@�@���y�_ �S��Ǝ���� �t�H�� 2001-���ő�1���@�� �@�@�@Johann Joseph Fux�@���n���E���[�t�E�t�b�N�X�@1660-1741 �@  �@��J.J.�t�b�N�X ��{�Ǘ��� �ÓT�Έʖ@ ���F ���a53-2���@�� �@�@�@Jean Le Rond d'Alembert�@�W�����E���E�����E�_�����x�[���@1717�`1783 �@ 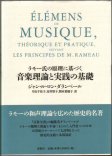 �@���W�����E���E�����E�_�����x�[�� �ЎR����q ����q�q �֖{�ؕ�q�� �@�@�@�����[���̌����Ɋ�Â� ���y���_�Ǝ��H�̊�b �t�H�� 2012�N ����-��1���@�� �@�@�@Johann Philipp Kirnberger�@���n���E�t�B���b�v�E�L�����x���K�[�@1721�`1783 �@  �@�����n���E�t�B���b�v�E�L�����x���K�[ ���쐴��� ������Ȃ̋Z�@ �t�H�� 2007-����1���@�� �@�@�@Luigi Cherubini�@���C�[�W�E�P���r�[�j�@1760�`1842 �@  �@���P���r�[�j ���b��M���� �Έʖ@�ƃt�[�K�u�� �A���e�X�p�u���b�V���O 2013-���ő�1���@�� �@�@�@����\���� �@�@�@Johann Christian Lobe�@���n���E�N���X�e�B�A���E���[�x�i���[�u�j �@�@�@1797�N5��30�� ���C�}�[���` 1881�N7��27�� ���C�v�c�B�q�@�h�C�c�̍�ȉƁA���y���_�ƁB �@�@�@1810�N�Ƀ��C�}�[���{��nj��y�c�̃��@�C�I���j�X�g��t���[�g�t�҂ɂȂ�A �@�@�@1811�N�Ƀ��C�}�[���nj��y�c�ɉ�������B �@�@�@�ނ�1819�N�ȑO�ɑ����̉��y��i����Ȃ��A �@�@�@1821�N�ɃI�y���u���B�b�e�L���g�v�ō�ȉƂƂ��ăf�r���[���A �@�@�@���̌�ADieFlibustier(1830)��Die Furstin von Granada(1833)�A �@�@�@����т������̃I�[�P�X�g����i���܂ޑ��̑����̍�i�������܂����B �@�@�@1842�N�܂���1845�N�̂����ꂩ�ŁA�ނ̓��C�}�[���nj��y�c�ł̒n�ʂ����ނ��A �@�@�@�����ɔC������A1846�N�Ƀ��C�v�c�B�q�Ɉڂ�A�����ō�ȋ��t����щ��y�]�_�ƂƂ��ē����܂����B �@�@�@�ނ͍����A���y�Ɋւ��钘��ōł��悭�L������Ă���A���̒��Ŕނ̍ł��d�v�ȍ�i�͉��y�̋��ȏ��A4���B �@�@�@ �@�@�@Werner Neumann�@���F���i�[�E�m�C�}���@ �@�@�@1905�N1��21�� �U�N�Z���B�P�[�j�q�V���^�C�� �` 1991�N4��24�� ���C�v�c�B�q�@�@�h�C�c�̉��y�w�ҁB �@�@�@1950�N11��20���Ƀ��C�v�c�B�q�E�o�b�n�E�A�[�J�C�u�Y��ݗ����A �@�@�@���n���E�[�o�X�e�B�A���E�o�b�n�S�W�̑�2�łł���m�C�G�E�o�b�n�E�A�E�X�K�x�̎�C�ҏW�҂ł����B �@  �@�����[�x�^�m�C�}�� ���{���i�� ���y�ʘ_ �ⓚ�`���ɂ�� ���F 1979-14���@�w�ɕϐF �@�@�@Louis Hector Berlioz�@���C�E�G�N�g���E�x�����I�[�Y�@1803-1869 �@  �@���x�����I�[�Y �Ð���� ���� �nj��y �w���@ �V���� 1929�N�����a4�@�� �@�{�̂̔w�����Ɍ�����������̏��݂���B �@�@�@Louis Hector Berlioz�@���C�E�G�N�g���E�x�����I�[�Y�@1803-1869�@�^�@ �@�@�@Richard Georg Strauss�@���q�����g�E�Q�I���N�E�V���g���E�X�@1864-1949 �@  �@���G�N�g�[���E�x�����I�[�Y�^���q�����g�E�V���g���E�X ���b��M���ďC �L������ �nj��y�@ �@�@�@���F 2006-1���@�� �@�@�@Ernst Friedrich Richter �G�����X�g�E�t���[�h���b�q�E���q�e���@1808-1879 �@  �@ �@ �@���G�����X�g�E�t���[�h���b�q�E���q�e������ �A���t���b�h�E���q�e������ ����ԑ��Y�Z�{ ��c����� �@�@�@�V���a���w ����y��X 1927�N�����a2�N10���@(��5��)�@���@�l�� �@�@�@��� �@�@�@�@��301�ŖڂɁu���w�ܑ�v�̘X������������A �@�@�@�@��������́yC���z�l�������Ɨ��ʂ́y�z�����ɂ��ꂼ�ꔼ���قNJ|�����Ă��܂��B �@�@�@�@�������Ɏ��ɓ��ł��A���̕����̃R�s�[�������̂�����܂��̂ł��t�����܂��B �@�@�@�@�X�������������܂�������������̐����H���ɂ����āu�X��̕s�����v�����ɍ�����A���̕�������������ԂɂȂ邱�ƁB �@������ԑ��Y�� �V���a���w ���� ����y��X 1929�N�����a4�N(�Ĕ�)�@�J�o�[�@�� �@�@�@Salomon Jadassohn�@�U�[�������E���[�_�X�]�[���@1831-1902 �@  �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@���U�[�����[���E���_�[�X�]�[�� �����O�Y�� �a���w���ȏ� (����\����) ���J���� ���a4�N�@ �@�@�@�J�o�[�@���@���Ԃ��h�̂ǁh�ɃC�^�~ �@������ԑ��Y�� ���[�_�[�\�[���� �a���w���ȏ� ���̌� ���v���Џ��X ��5 �@�����[�_�\�[�� ����ԑ��Y�� �Έʖ@���ȏ� ���v���Џ��X ���a6�N�@�� �@��S.���_�X�]�[�� �˓c�M�Y�� �J�m���ƃt�[�K �T���Ȃ���ѓّ��ȋ��� ���F 1971-2�� �@�@�@Adolphe Leopold Danhauser�@�A�h���t�E���I�|���h�E�_���m�[�[���@1835-1896�@ �@�@�@�@�^�@ Henri�@Rabaud�@�A�����E���{�[�@1873-1949 �@  �@��A.�_���m�[�[���^�A�����E���{�[���� �������� ���y���_ �D�y�� ��8�@���@ �@�@�@���@�\���i���������j���w�����Ō��������Ă���{�̂���ꗎ�����O��� �@�@�@Francois-Clement Theodore Dubois�@�t�����\�����N���}���E�e�I�h�[���E�f���{���@1837-1924 �@ 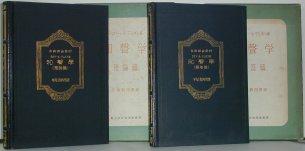 �@���e�I�h�[���E�f���{�A �����M�l�j�� �a���w (���_�сE�т̓��) 1954-���� �n���� �� �@   �@���e�I�h�[���E�f���{���@�����M�l�j��@���H�Y�Z������@�a���w (���_�сE���{�т̓��)�@ �@�@�@���F�@1978-1���@�r�j�J�o�[�@�� �@�@�@Ernest Guiraud�@�G���l�X�g�E�M���[�@1837-1892�@�^�@Henri Busser�@�A�����E�r���b�Z���@1872-1973 �@  �@���G���l�X�g�E�M���[�^�A�����[�E�r���b�Z�� �r���F���Y�� �y��Ґ����p�T�_ �S�� 2001-��1��3�� �@�@�@�X��⑫�@1953�����a28�ɋ���o�ł�蔭�s����A���̂܂܂̓��e�őS������Ċ����ꂽ���́B �@�@�@Nikolai Andreyevich Rimsky-Korsakov�@�j�R���C�E�A���h���C�F���B�`�E�����X�L�[���R���T�R�t�@1844-1908 �@ 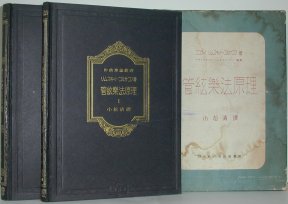 �@ �@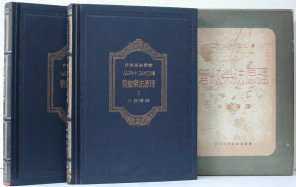 �@���j�R���C �����X�L�C�[�R���T�R�t�@�}�L�V�~���A�� �V���^�C���x���N�� �������� �nj��y�@���� �@�@�@�n���� ���a14 �@���j�R���C �����X�L�C�[�R���T�R�t�@�}�L�V�~���A�� �V���^�C���x���N�� �������� �nj��y�@���� �@�@�@�n���� ���a30-�ĔŁ@��̏������� �@�@�@�X��⑫�@���s��͐�O�́y���a14�N�Łz�ː��Ċ�����y���a25�N���Łz�ˁy���a30�N�ĔŁz�ƂȂ��Ă��܂��B �@�@�@��O�łƐ��ł̈Ⴂ�͂����ꕔ�̕��͉��������łɌ�������x�ł��B �@  �@ �@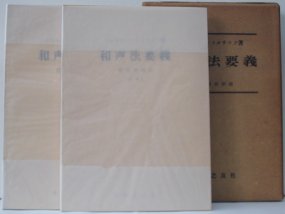 �@�������X�L�C�E�R���T�R�t ���������Y�� �a���@���K ������ ���a21-6�Ł@�l���ƏZ���������� �@�������X�L�[�E�R���T�R�t �������N�� �a���@�v�` (�{���ƒ��̓��) ���F ���a28�@�� �@�@�@Charles-Marie Jean Albert Widor�@�V���������}���[�E���B�h�[�� 1844-1937 �@  �@��CH.M.�r�h�[�� �˒J�W�O�� �ߑ�nj��y�@ �S�� 1962�@�� �@�@�@Paul Marie Theodore Vincent d'Indy�@�|�[���E�}���E�e�I�h�[���E���@���T���E�_���f�B�@1851-1931 �@�@  �@�����@���T���E�_���f�B �r���F���Y�� ��Ȗ@�u�` ����o�Ł@�� �@�@�@�@��ꊪ�@���a28 �@�@�@�@���㊪�@���a30 �@�@�@�@����@���a31 �@�@�@�X��⑫�@����(�ŏI��)�͖����B �@�@�@�u��Ȗ@�u�`�̌Éꏑ�X���v���ɂ���A������̃y�[�W �ɂĔ����Ă���܂��B �@�@�@Charles Villiers Stanford�@�`���[���Y�E���B���A�[�Y�E�X�^���t�H�[�h�@1852-1924 �@  �@���X�^���t�H�[�h���� ��n���q��q ��Ȗ@ ���c���ē� �吳14�@���@ �@�@�@�\���ɖڗ��V�~��L�Y�@���Ԃ��ɋL���炵������ �@�@�@Percy Goetschius�@�p�[�V�[�E�Q�[�e�B�A�X�@1853-1943 �@  �@���p�[�V�[�E�Q�[�e�B�A�X ������ �r�K�i���� ������Ȗ@ ���m�}�� ���a5 �@�@�@��6�ŁA��94�ŁA��139�łɏ����݁@������̌��Ԃ���"�̂�"�����ɂ݁@������ �@�@�@William James Foxell�@�E�B���A���E�W�F�[���Y�E�t�H�N�Z���@1857-1933 �@  �@���E�B���A���E�W�F�[���Y�E�t�H�N�Z�� �����p�m�� ���y�̊ӏܖ@ (���y�Ϗ܂̌���) �@�@�@���y���[ 1936�����a11 �J�o�[�����@8�łقǂɐ���?�̏������Ղ��� �@�@�@Ludwig Thuille�@���[�h�E�B�q�E�g�D�C���@1861-1907�@�^�@Rudolf Louis�@���[�h���t�E���C�@1870-1914 �@  �@�����[�h�E�b�q�E�g�D�C���^���[�h���t�E���C �R����� �n���q�� �a���w ���F 1972(��47)-4�� �@�@�@�J�o�[�ɏ���Ə����u�P �@�@�X��⑫ �@�@�@�����̉��y�V�F�Ђ̂��̖{�̐�`�������̂܂܍ڂ��܂��B �@�@�@�w���_�I�ł���Ɠ����Ɏ��ۓI�ł���A�w�K�҂����K�ɂ������Ē��ʂ���^��ɑ��ɂ߂Đe�ɁA �@�@�@�����̎�����f���Đ��������B�a���w�ō��̏��ƒ�]������B�x �@�@�@Steplan Krehl�@�V���e�t�@���E�N���[���@1864-1924 �@ 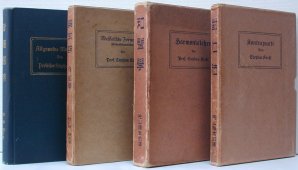 �@ �@ �@���X�e�t�@���E�N���[�� �M���� �ЎR�o���Y�� ���y�ʘ_ ����y��X ���a2�N�@������ �@���X�e�t�@���E�N���[�� �M���� �ЎR�o���Y�� ������ �y���_ (��Ȋw) ����y��X ���a15�N�@������ �@���X�e�t�@���E�N���[�� �ЎR�o���Y�� �a���w ����y��X ���a7�N�@������@�� �@���X�e�t�@���E�N���[�� �ЎR�o���Y�� �Έʖ@ ����y��X ���a4�N�@������@�� �@���X�e�t�@���E�N���[�� �����p�m �������� ���y�̈�ʒm�� (���y�T��) ���y���[ ���a8�N(1933)�@ �@�@�@�J�o�[�����@6�łقǂɏ����݂Ƃ��̏����ՁA���Ԃ��ɕ����̏������Ղ���B �@�@�@Franz Mayerhoff�@�t�����c�E�}�C�G���z�b�t�@1864-1938 �@  �@���}�C�G���z�b�t �M���� �ЎR�o���Y�� �nj��y��_ ���{�y���Џo�ŕ� ���a16-3�Ł@�� �@�@�@Emile Jaques-Dalcroze�@�G�~�[���E�W���b�N���_���N���[�Y�@1865-1950 �@  �@ �@ �@���G�~�[���E�W���b�N=�_���N���[�Y �약��� ���g�~�b�N�_���W ���Y���Ɖ��y�Ƌ��� �S�� 1975�@ �@�@�@���@�� �@���W���[�E�y�j���g�� ��H���� ���������� �_���N���[�Y�̗������� ���������w�@ 1930�N = ��5 �@�@�@Charles Koechlin�@�V�������E�P�b�N�����@1867-1951 �@  �@ �@ �@ �@�@��Ch.�P�b�N���� �����C�� �a���̕ϑJ ���F 1962-1�� �@��Ch.�P�b�N���� �����C�� �Έʖ@ ���F 1968-1�� �@�@�@Anna Heuermann-Hamilton�@�A���i�E�z�C���[�}��=�n�~���g�� �@�@�@1867�N9��16���i�O���S���I��j�V�J�S �` 1959�N7��8���Ȃ����͓��N7��9�� �}�[�V���� �@�@�@�A�����J�̃s�A�j�X�g�A���y���t �@�@�@���C�X�E�I�X�e��/�n���\�����C���h/�N�������X�E�G�f�B/�t���f���b�N�E�O�����g�E�O���[�\���̊w�� �@�@�@�@�@�M��{�Ɂ@�]���̂̒e�t�@ �@�@�@�@�@�G�[�E�G�[�`�E�n�~���g�� �� ; ���C�X�E�N�[�p�[, ���c���q ���� �@�@�@�@�@�����ُo�ŕ� ���a9 38p�@������B �@  �@���G�[�E�G�[�`�E�n�~���g���v�l �͕��ٕ� ���Տ�̘a���w�ƈڒ��@ ������ �h���� 1936(���a11) �@�@�@Henri Busser�@�A�����E�r���b�Z���@1872-1973 �@  �@���A�����[�E�r���b�Z�� �r���F���Y�� ��Ȓ�v ���y�� ����o�� ���a28�@ �@�@�@�ѕt�ł����єw�ɖڗ��ꍞ�݂���A�l��A���t����B �@�@�@�X��⑫�@�`���Ɂy�o�Ŏ҂̊o���z�Ƃ��ē����҂́u�y��Ґ����p�T�_�v��⑫������́v�Ƃ���B �@�@�@�n���Y�@? - ? �@  �@���n���Y�� ��Ȃ̎d�� ���J���� �吳14�@������@���Ԃ��̒Ԃ������┟�ɖڗ��C�^�~ �@�@�@�X��⑫�@�u���v�� �̗w��ȉƃA�[�l�X�g�E�j�E�g��Ernest Newton�́u�̗w��Ȗ@�v�̑S��� �@�@�@��҂̔n���Y�����M�����ҏ��Ƃ̋L�q������B �@�@�@Max Reger�@�}�b�N�X�E���[�K�[�@1873-1916 �@  �@ �@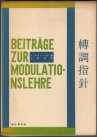 �@���}�b�N�X�E���[�K�[ �ЎR�o���Y�� �z��(�]��)�@�̍���� ����y��X ���a3 �@���}�b�N�X�E���[�K�[ �������� �z��(�]��)�w�j �����n���� ���a34 �@�@�@Hugo Leichtentritt�@�t�[�S�[�E���C�q�e���g���b�g�@1874-1951 �@  �@���t�[�S�[�E���C�q�e���g���b�g ���{���i�� ���y�̌`�� ���F 1980����55-10�� �@�@�@Arnold Schonberg�@�A���m���g�E�V�F�[���x���N�@1874-1951 �@ 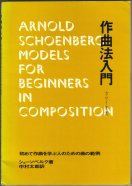 �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@���V�F�[���x���N �������Y�� ��Ȗ@���� ���߂č�Ȃ��w�Ԑl�̂��߂̋Ȃ̔͗� �@�@�@�J���C�y�� ���a41-1���@�r�[���J�o�[���� �@���A���m���g�E�V�F�[���x���N�@G.�X�g�����O�^L.�X�^�C���� �R�p�Α��Y �����^��� ��Ȃ̊�b�Z�@ �@�@�@���F ��46-1�� �@���A���m���g�E�V�F�[���x���N ��c���� �a���@ ���F 1968-1���@���t�ƋL������ �@���A���m���g�E�V�F�[���x���N ��c���� �V�� �a���@ �a���̍\���I���@�\ �����\���� ���F 1982-1�� �@�@�@�X��⑫�@�u���������łɂ��ƂÂ��V��Łv�ƋL������Ă���܂��B �@���A���m���g�E�V�F�[���x���N�@���i�[�h�E�X�^�C���� �R�p�Α��Y �����^��� �Έʖ@���� �@�@�@���F ���a53-1�� �@�@�@Richard Stohr�@���q�����g�E�V���e�[���@1874-1967 �@  �@ �@ �@ �@ �@���V���e�[�� ���[���� ���y�`���w ���F ���a63-15���@�� �@��R.�V���e�[�� ���������� �a���@ �S�� 1968�@�� �@�����q�����g�E�V���e�[�� �������Y�� �Έʖ@ �S�� ���a50-13�Ł@�� �@�@�@Arthur Eaglefield Hull�@�A�[�T�[�E�C�[�O���t�B�[�h�E�n���@1876-1928 �@ 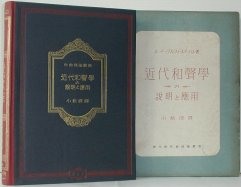 �@ �@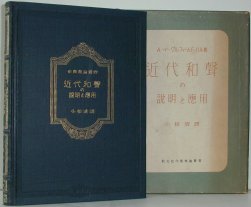 �@���A�[�T�[�E�C�[�O���t�B�[���h�E�n�� �������� �ߑ�a���̐����Ɖ��p �n���� ���a14�@�� �@���A�[�T�[�E�C�[�O���t�B�[���h�E�n�� �������� �ߑ�a���̐����Ɖ��p �n���� ���a27�@�� �@�@�@�X��⑫�@��O�y���a14�N�Łz�̍Ċ��łƂȂ�A���̍Ċ��ł̒��Łu�����̒��������݂��v�Ɩ�҂̋L�ڂ���B �@�@�@Adam Carse�@�A�_���E�J�[�Y�@1878-1958 �@  �@���A�_���E�J�A�X ��c�����Y�� �nj��y�y�ъnj��y�@�̗��j�I���� ��ꏑ�[ ���a11-�ĔŁ@�� �@�@�@Rudolph Reti�@���[�h���t�E���e�B�@1885-1957 �@  �@�����[�h���t�E���e�B ����M�j �ݖ{�G�q�� ���Ȃ̐����w �N���V�b�N���y�̎��Ƒg���� �@�@�@���F 1999-2�� �@�@�@Marcel Dupre�@�}���Z���E�f���v���@1886-1971 �@  �@���}���Z���E�f���v�� �r���F���Y�� �Έʖ@�ƃt���[�O ���y�� ����o�� ���a32�@ �@�@�@���@�\���ɖڗ�������̕\��̏��݁@�w�p��5�p�̐� �@�@�@Reginald Owen Morris�@���W�i���h�E�I�[�G���E�����X�@1886-1948 �@  �@ �@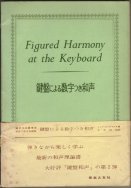 �@��R.O.�����X �������� �a���w�ƑΈʖ@�̊�b ���y���[ 1935�����a10�N�@ �@�@�@���@��1�Ƒ�3�łɐ���������B�J�o�[�w��2�p��̌��Ɨɔ������u�P�����B �@�����W�i���h.O.�����X ����~���� ���Ղɂ�鐔�����a�� ���F ���a36�@�� �@�@�@Hermann Grabner�@�w���}���E�O���[�u�i�[�@1886-1969 �@  �@���w���}���E�O���[�u�i�[ ��{���傤�� �|���ӂݎq�� ���ׂĂ��킩�鉹�y���_ ���ȉƒ��S�@ �@�@�@�V���t�H�j�A 1996-1�� �@�@�@Ernst Toch�@�G�����X�g�E�g�b�z�@1887-1964 �@  �@���G�����X�g�E�g�b�z ���슰�C�� �����w ���F ��47-5�� �@�@�@George Anson Wedge�@�W���[�W�E�A���\���E�E�F�b�W�@1890�N1��15�� �č� �R�l�`�J�b�g�B �_���x���[ �` 1964�N11�� �@�@�@1939�N����1946�N�܂ŃW�����A�[�h���y�@�̊w�����߂��A�����J�̉��y��ƁB �@  �@ �@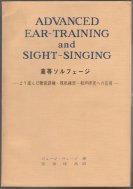 �@���W���[�W�E�E�F�b�W �약�� ���Տ�̘a�� �������y��w�o�ŕ� 1964-�ĔŁ@����� �@���W���[�W�E�E�F�b�W �{�c������ �����\���t�F�[�W ���i���o�P���E�������K�E�a�������ւ̉��p �@�@�@�������y��w�o�ŕ� 1967-2���@�J�o�[�Ȃ��@������ �@�@�@John Barham Johnson �@�W�����E�o�[�n���i�o�[�����j�E�W�����\���@1890 - 1965 �@�@�@�E�B���U�[�̐��W���[�W���̑��w�Z�A�P���u���b�W�̃Z���E�B���E�J���b�W�i�P���u���b�W��w�̍\����w�j�Ŋw�ԁB �@�@�@1933�N�A�I�[�N�n�����拳��I���K�j�X�g�B �@ 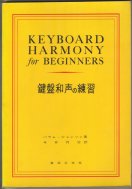 �@���o�����E�W�����\�� �iJ.Barham Johnson�j ����~���� ���a���̗��K ���F ��47-10�� �@�@�@Hans Mersmann�@�n���X�E�����X�}���@1891-1971 �@  �@���n���X�E�����X�}�� ���A�q�Y�� ���y�ʘ_ ��ꏑ�[ ��15-2���@�������������� �@�@�@Noel Gallon�@�m�G���E�M�������@1891-1966�@�^�@Marcel Bitsch�@�}���Z���E�r�b�`���@1921-2011 �@  �@���m�G�����M�������^�}���Z���E�r�b�`�� ���H�Y�� �Έʖ@ ���F ��60-11���@�r�j�J�o�[�@�� �@�@�@Knud Jeppesen�@�N�k�[�g�E�C�F�b�y�Z���@1892-1974 �@ 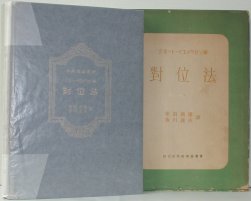 �@ �@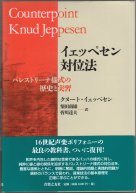 �@���N�k�[�g�E�C�G�b�y�Z�� �ēc��Y �F��B�v�� �Έʖ@ �n���� ���a30-���Ł@�� �@���N�k�[�g�E�C�F�b�y�Z�� �ēc��Y �F��B�v�� �Έʖ@ �p���X�g���[�i�l���̗��j�Ǝ��K �@���F 2013-1���@�� �@�@�@�X��⑫�@�u���a30�N�Łv���e�ł��̂܂ܕ����������́B �@�@�@Josef Rufer�@���[�[�t�E���[�t�@�[�@1893-1985 �@  �@�����[�[�t�E���[�t�@�[ ����`�Y�� 12���ɂ���ȋZ�@ ���F 1980-7�� �@�@�@Willi Apel�@�E�B���[�E�A�[�y���@1893-1988 �@  �@���E�B���[�E�A�[�x�� ���쐴��� �|���t�H�j�[���y�̋L���@ 1450�`1600 �@�@�@�t�H�� 1998-���ő�1���@�� �@�@�@Walter Piston�@�E�H���^�[�E�s�X�g���@1894-1976 �@  �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@���E�H���^�[�E�s�X�g�� �q���r�v�� �a���w �n���� 1956-���Ł@�� �@���E�H���^�[�E�s�X�g���@M.�f���H�[�g(�������) �p�q��N�� �a���@ ���͂Ǝ��K ���F 2006-1���@�� �@���E�H���^�[�E�s�X�g�� �p�q��N�� �Έʖ@ ���͂Ǝ��K ���F 2009-1���@�� �@���E�H���^�[�E�s�X�g�� �˓c�M�Y�� �nj��y�@ ���F 2005-26�� �@�@�@Amy Dommel Die'hy�@�A�~�C�E�h������=�f�B�G�j�@1894-1981 �@  �@���A�~�C�E�h������=�f�B�G�j �X�䜨���q�� �����Ă���a�� �����I�a�� ���F ���a42-1�� �@�@�@ Gordon Jacob�@�S�[�h���E�W�F�C�R�u�i�S�[�h���E���R�u�j�@1895-1984 �@ 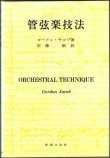 �@���S�[�h���E���R�u �@���h �nj��y�Z�@ ���F 2005-29�� �@�@�@Paul Hindemith�@�p�E���E�q���f�~�b�g�@ 1895-1963 �@ 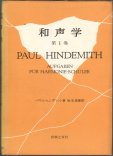 �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@���p�E���E�q���f�~�b�g ��{�Ǘ��� �a���w ��T�� ���F ���a43-5�� �@���p�E���E�q���f�~�b�g ��{�Ǘ��� �a���w ��U�� ���F ���a54-2���@�J�o�[�w�ϐF �@���p�E���E�q���f�~�b�g ����ᨈ�� ��Ȃ̎���� ���F ���a51-2�� �@���p�E���E�q���f�~�b�g ����ᨈ� �u��Òj�� ���y�Ȃ̗��K�� ���F ���a46-2�� �@�@�@�X��⑫�@�y��Ȃ̎�����z���_�т̑����ɂ�������n�тƂȂ��Ă܂��B �@���p�E���E�q���f�~�b�g ��{�Ǘ� �瑠���Y�� �V�� ���y�Ƃ̂��߂̊�b���K ���F ���a42-8�� �@�@�@Victor Zuckerkandl�@���B�N�g���E�c�b�J�[�J���h���@1896-1965 �@  �@�����B�N�g���E�c�J�[�J���h�� �n���K�O�Y ��J�I���q�� �J���W��ďC ���y�̑̌� ���y���킩��Ƃ� �@�@�@���F 1982-1�� �@�@�@�Z�~�����E�G�������m���B�`�E�}�N�V���t�@1898-? �@  �@��S.�}�N�V���t ������Y�� �s�A�m�ɂ��a���̗��K �\���B�G�g�̃s�A�m���� �@�@�@���W�J�m�[���@ 1982�N-1�� �@�@�@ Ernst Krenek�@�G�����X�g�E�N���V�F�l�N�@1900-1991 �@  �@ �@ �@��E.�N�V�F�l�N ��c���� �Έʖ@ �\�����I�X�^�C���ɂ�� �����R���M�E�� 1977�N�� �@���G�����X�g��N�V�F�l�[�N�@�@���h�� �\�Z�@�Ɋ�Â��Έʖ@�̌��� ���F 1955�����a30 �@�@�@�@�u�\�Z�@�Ɋ�Â��Έʖ@�̌����v�����ȊO�ɂ��ɂ���A������̃y�[�W �ɂĈ�_��������Ă��܂��B �@�@�@Joseph Smits van Waesberghe�@�X�~�b�c�E���@���E���@�X�x���Q�@1901-1986 �@  �@���X�~�b�c�E���@���E���@�X�x���Q ���쐴��� �������_ ���F 1976-1���@���Ԃ��ɏ��� �@�@�@Edmond Costere�@�G�h�����E�R�X�e�[���@1905�N5��2���i�O���S���I��j �` 2001�@�@���y�w�� �@  �@���G�h�����h�E�R�X�e�[�� ���{������ �a���̕ϖe �����g�D�̘_�� ���F 1980-1���@�� �@�@�@Paul Creston�@�|�[���E�N���X�g���@1906-1985 �@  �@���|�[���E�N���X�g�� ����O��Y�� ���Y���̌��� ���F 1978-5�� �@�@�@Siegfried Borris�@�W�[�N�t���[�g�E�{���X�@1906-1987 �@  �@���W�[�N�t���[�g�E�{���X �c���M�F �i�c�F�M�� �a���@ �l�����A�w�ѕ��A������ �V���t�H�j�A 1999 �@�@�@Yvonne Desportes�@�C���H���k�E�f�X�|���e�X�@1907�N7��18�� �` 1993�N12��29�� �@�@�@�t�����X�̍�ȉƁA��ƁA���y����ҁB �@�@�@�h�C�c�̃R�[�u���N�ŁA��ȉƂ̃G�~�[���E�f�X�|���e�X�Ɖ�Ƃ̃x���^�E�g�����G�b�v�̊Ԃɐ��܂ꂽ�B �@�@�@�|�[���E�f���J�X�̊w���ł���A1932�N�Ƀv���~�A�O�����v���h���[�}�ŗD�������B �@�@�@�p�����y�@�ŋ����A�����̉��y���ȏ��������A������500�ȏ�̍�i����Ȃ����B �@�@�@Alain Henri Bernaud�@�A�����E�A�����E�x���m�[�@1932�N3��8�� �` 2020�N12��4�� �@�@�@�t�����X�̍�ȉƁB �@�@�@��ȍ�i�̂Ȃ��ɂ̓T�N�\�t�H�[���l�d�t�Ȃ�����B �@  �@���C���H���k�E�f�|���g�^�A�����E�x���m�[ �i�x���V �i�x�a�q�� �a���@ ��b���_ ���ȉƂ̘a���l�� �@�@�@�������y�o�� 1990-���� �@�@�@Jacques Chailley�@�W���b�N�E�V���C�G 1910-1999 �@  �@���W���b�N�E�V���C�G ���c�K�Y ��K�B�� ���y���� �M���V�����@���猻�㉹�y�܂� ���F ���a43-1���@ �@�@�@�r�j�J�o�[�@�� �@�@�@Jacques Chailley�@�W���b�N�E�V���C�G 1910-1999�@�^�@Henri Challan�@�A�����E�V�������@1910-1977 �@  �@��J.�V���C�G�^H.�V���������� �r���F���Y�� ���y�̑����_ �㊪ ����o�� ���a31�@�� �@�@�@�X��⑫�@�����͖����ƂȂ��Ă��܂��B �@�@�@Grosvenor W.Cooper�@�O���[���i�[�EW.�N�[�p�[�@1911 �` 1979�@�iGrosvenor William? Cooper�j �@�@�@�V�J�S��w�̋����A1970�N���ɑސE�B �@�@�@���Ɂu���������w�Ԃ��Ɓv �@�@�@Leonard B.Meyer�@���i�[�h�EB.�}�C���[�@1918�N1��12���j���[���[�N �` 2007�N12��30�� �j���[���[�N �@�@�@�A�����J�̍�ȉƁA���y�w�ҁA�N�w�ҁB���y���w��y�ȕ��͂̕���ŏd�v�Ȓ�����c�����B �@�@�@�}�C���[�̓R�����r�A��w�Ŋw�сA�N�w�̊w�m���Ɖ��y�̏C�m�����擾���܂����B �@�@�@�ނ̓V�J�S��w�Ŋw�сA1954�N�ɕ����j�̔��m�������^����܂����B �@�@�@��ȉƂƂ��ẮA�V���e�t�@���E���H���v�A�I�b�g�[�E���[�j���O�A�A�[�����E�R�[�v�����h�Ɏt���B �@�@�@1946�N�ɃV�J�S��w�̉��y�w���̃����o�[�ɂȂ�A1961�N�ɃV�J�S��w�̉��y�����ɔC������A �@�@�@1975�N�Ƀy���V���x�j�A��w�̉��y�Ɛl���Ȋw�̋����ɔC������܂����B �@�@�@1988�N�Ƀy���V���x�j�A�B�̖��_�����ɂȂ�܂����B �@  �@ �@ �@��G.W.�N�[�p�[�^L.B.���C���[ ���ۋg�F�� ���y�̃��Y���\�� ���F 1975-3�� �@�@�X��⑫�@���́y��3���Łz�̖�҂��Ƃ����Ɂu��2���ɂ������āA����s�K�ȕ\���͂ł��邩����Ȃ������v�Ƃ���܂��B �@��G.W.�N�[�p�[�^L.B.�}�C���[ ���ۋg�F �k�쏃�q�� �V�� ���y�̃��Y���\�� ���F 2001-1�� �@�@�X��⑫�@�y�V��Łz�̖�҂��Ƃ����ł́u�C�����ׂ��_�������������̂ŁA�V�����|��ŏo�ł��������v�Ƃ���܂��B �@�@�@ Vincent Persichetti�@���B���Z���g�E�p�[�V�P�b�e�B�@1915-1987 �@  �@�����B���Z���g�E�p�[�V�P�b�e�B ����v��Y�� 20���I�̘a���@ ���F ��45-3�� �@�@�@Humphrey Searle�@�n���t���[�E�T�[���i�n���t���[�E�Z�A�[���j�@1915-1982 �@ 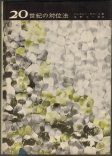 �@���n���t���[�E�Z�A�[�� ����v��Y�� 20���I�̑Έʖ@ �w���̂��߂̎�т� ���F 1970-3�� �@�@�@Robert Erickson�@���o�[�g�E�G���N�\���@1917 - 1997 �@  �@�����o�[�g�E�G���N�\�� ��c�w���� ���y�̍\�� �����E�Έʖ@�̌��� �|�p����� 1986-���Ł@ �@�@�@�r�j�J�o�[�@�� �@�@�@Olivier Alain�@�I�����B�G�E�A�����@1918-1994 �@  �@���I�����B�G�E�A���� �i�x���V ��{���V�� �a���̗��j ���������ɃN�Z�W�� 2007-17�� �@�@�@Walter Gieseler�@���@���^�[�E�M�[�[���[�@1919-1999 �@  �@�����@���^�[�E�M�[�[���[ ������i�� 20���I�̍�� ���㉹�y�̗��_�I�W�] ���F 1988-1���@�� �@�@�@S.J.Jose Ignacio Tejon�@�z�Z�E�C�O�i�`�I�E�e�z���@1920-? �@  �@���z�Z�EI.�e�z�� �p���X�g���[�i�l���ɂ��Έʖ@ ������ ���F 1996-������14�� �@�@�@����`�Y�@1921-1980 �@  �@������`�Y �\�̉��y �V�F�[���x���N�Ƃ��̋Z�@ ���쏑�[ ��28�N�@������@���M�ɂ����� �@�@�@ Marcel Bitsch�@�}���Z���E�r�b�`���@1921-2011 �@ 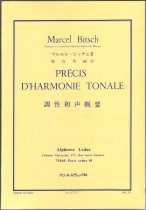 �@���}���Z���E�r�b�`�� �ѓ��p�k�� �@�@Precis d'Harmonie Tonale�@(Pour by traduction Japonaise) �����a���T�v Alphonse Leduc 1986 �@�@�@�X��⑫�@�p�� - �A���t�H���X�E���f���b�N�Ђ�����������̂ŐV�i (�\���ɓ����艚�݂���܂�) �@�@�@Marcel Bitsch�@�}���Z���E�r�b�`���@1921 �` 2011 �@�@�@Jean-Paul Holstein�@�W�������|�[���E�I���X�^�C���@1939�N�N11��6���ɃA���O���[�� �` ? �@�@�@�t�����X�̍�ȉ� �@ 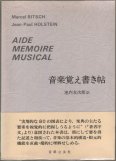 �@���}���Z���E�r�b�`���^�W����=�p�E���E�I���X�^�C�� �r���F���Y�� ���y�o�������� ���F 1979-1�� �@�@�@�r�j�J�o�[ �� �@�@�@Marcel Bitsch�@�}���Z���E�r�b�`���@1921 �` 2011 �@�@�@Jean Bonfils�@�W�����E�{���t�B�X�@1921 �` 2007 �@  �@���}���Z���E�r�b�`�^�W�����E�{���t�B�X �r���F���Y�ďC�� �]�c���L�� �t�[�K �@�@�@���������ɃN�Z�W�� 2006-6�� �@�@�@Andre Hodeir�@�A���h���E�I�f�[���@1921�N1��22���p�� �` 2011�N11��1���x���T�C�� �@�@�@�t�����X�̃��@�C�I���j�X�g�A��ȉƁA�ҋȉƁA���y�w�ҁB �@  �@���A���h���E�I�f�[�� �g�c�G�a�� ���y�̌`�� �����V�� ���������ɃN�Z�W�� 2005-25�� �@�@�@Erhard Karkoschka�@�G�A�n���g�E�J���R�V���J�@1923-2009 �@  �@���G���n���g�E�J���R�V���J ����`�N�� ���㉹�y�̋L�� �S�� 2002 ��1��-7�� �@�@�@Ludwig Karl Weber�@���[�g���B�q�E�J�[���E���F�[�o�[�@1924 �` �@  �@ �@ �@ �@ �@�����[�g���B�q�E�J�[���E���F�[�o�[ �c���M�F�� ���t�̂��߂̉��y�ʘ_ �V���t�H�A 1990-1���@ �@�@�@�r�j�J�o�[ �@�����[�g���B�q�E�J�[���E���F�[�o�[ �g�c��v�ďC ��{�V���E�W�� ���t�̂��߂̌`���_���� �@�@�@�V���t�H�j�A 1988-1���@�r�j�J�o�[ �@�����[�g���B�q�E�J�[���E���F�[�o�[ �c���M�F�� ���t�̂��߂̘a���@���� �V���t�H�A 1994-1�� �@�@�@Charles Rosen�@�`���[���Y����[�[���@1927-2012 �@  �@���`���[���Y����[�[�� �����~�� �\�i�^���`�� �A�J�f�~�A��~���[�W�b�N 1997-���� �@�@�@Diether de la Motte�@�f�B�[�^�[�E�f�E���E���b�e�@1928-2010 �@  �@ �@ �@ �@ �@���f�B�[�^�[�E�f�E���E���b�e �g�c��v�ďC ���h�q�� ���ȉƂ̘a�� �V���t�H�j�A 1980-1���@ �@�@�@�r�j�J�o�[ �� �@���f�B�[�^�[�E�f�E���E���b�e ����h�q�� ���ȉƂ̑Έʖ@ �V���t�H�j�A 1989 �@���f�B�[�^�E�f�E���E���b�e ����`�N�� ���y�̕���:�ᔻ�I���� �J�[���E�_�[���n�E�X �@�@�@ (�e�L�X�g�сE�y���т̓��) �S�� 1983�@�� �@�@�@Robert Vliegen�@���x���g�E�u���[�Q���@1929��-2005 �@  �@�����x���g�E�����[�Q�� �|���t�H�j�[�Ɍ��銽�� 9���I���16���I�Ԃł̑������y�j �ʍ���ȏW�t �@�@�@���F 1982-9�� �@�@�@���쐴�� �Ƃ����킹�������@1930 �` �@  �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@  �@ �@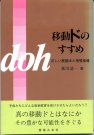 �@ �@ �@�����쐴�� �V���[�v�ƃt���b�g�̂͂Ȃ� �Ǖ��@�̍��� ���F 1993-1�� �@�����쐴�� ������m��Ȃ������y�T�̂͂Ȃ� ���F 1994-1�� �@�����쐴��� �Έʖ@�̕ϓ��E�V���y�̑ٓ� ���l�T���X����o���b�N�� �]�����̉��y���_ �@�@�@�t�H�� 2008-���ő�1���@�� �@�����쐴�� ���쏺�� ���y�L�[���[�h���T �t�H�� 1994-8 �@�����쐴���@�ނ��A�Â��e�u�Œ�h�v��I �\���~�[�[�V���������@���F�@1983-1���@ �@�@�@�J�o�[�w�ސF�@�� �@�����쐴��@�ړ��h�̂����� �������Ǖ��@�Ǝ����w���@���F�@1985-1���@�с@�J�o�[�w�ސF�@�с@ �@�@�@���提���� �@�����쐴��@�Ǖ��� �`���I�ȁu�ړ��h�v����V�X�e���Ɋw���@�t�H�Ё@2005-1���@�� �@�@�@Salvatore Nicolosi�@�T�����@�g�[���E�j�R���[�V�@1942 �J�X�g���m�[���H�E�f�B�E�V�`���A �` �@�@�@�g���m�������y�w�Z���ƁB��ȉƁA���y���_�ƁB80�N�����|�p��w���ŁA�a���E�Έʖ@�E���t�@��������B �@  �@���T�����@�g�[���E�j�R���[�V �����f�q:���{��Z�� 16���I�̎���Ɋw�� �ÓT�����Έʖ@ �@�@�@���F 1997-1�� �@�@�y���_�z�@���v�_���i���j��122�_ �@�@�@�i�㉺�����m ����1�_�Ƃ��Đ����Ă�����̂����邽�߁A���v�����͎�����܂��j |
||
| �@�@���_���̋Ɉꕔ�͂��̃y�[�W�ł͂Ȃ��A�u��ȉƁv�̃y�[�W�Ɉړ����Čf�ڂ��Ă�����̂�����܂��B �@�@�����̒I�ɂ�����Ǘ���̓s���ɂ����̂ł��B�i�f�ڂɏd���͂��Ă���܂���j |
||
���̃y�[�W��2025�N02��18���ɍX�V���܂����B |